言葉が遅いと心配になりますよね。他の子どもと比べてしまうこともあるでしょう。本記事では、1歳から3歳までの言葉が遅い子どもの特徴について解説します。発達の遅れがあるときに必要なサポート方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
1歳 言葉が遅い子どもの特徴と対策

1歳頃の子どもは、歩いたり走ったりと運動能力がぐんと発達する時期です。離乳食が完了して、食べ物への興味が広がる子もいます。
また、「ママ」「パパ」といった簡単な単語を話し始める子も増えますが、言葉の発達には個人差があり、まだ話さないからといって問題とは限りません。ほかの子と比べて不安になることもありますが、成長のスピードは一人ひとり違うので、ゆったりと見守ることが大切です。
言葉が遅い1歳児の特徴
言葉が遅い1歳の子どもには、次のような特徴があります。
- 言葉が出ない・少ない
- 指差しが少ない
- 音への反応が鈍い
- 興味が限定的
- 呼びかけても振り向かない
- 目を合わせない
1歳児で言葉が遅いと、「ママ」「パパ」と呼んでくれる日を楽しみにしている分、少し心配になりますよね。特に、公園や支援センターで出会う同じくらいの年齢の子どもが「ママ」「パパ」と話していると、羨ましくて焦ることもあるかもしれません。
でも、まだ個人差が大きい時期なので、焦らなくても大丈夫です。かわいらしい仕草や笑顔もたくさん見られる時期ですから、ゆったりと見守りましょう。
言葉が遅い1歳児へのサポート方法
1歳児の言葉の遅れには、子どもが楽しめる絵本の読み聞かせが効果的です。動物や食べ物の名前がたくさん出てくる絵本を使い、子どもと一緒に絵を指差しながら「ワンワンだね」「りんごがあるね」と話しかけると、語彙が増えやすくなります。
また、「これなあに?」といった短い質問を投げかけると、子どもが返答したり身振りで伝えようとする力が育ちます。
音の出るおもちゃや手遊び歌は、子どもがリズムに乗って言葉を覚えやすくするのでおすすめです。無理に話させようとせず、子どもが楽しみながら取り入れてみてください。
なお、言葉が遅れている以外に気になることがある場合は、1歳児半検診で相談してみましょう。
2歳 言葉が遅い子どもの特徴と対策

2歳頃になると、自己主張が強くなり、走ったりジャンプしたりと運動能力もぐんと発達します。この時期は「イヤイヤ期」とも呼ばれ、好き嫌いがはっきりしてくるのも特徴です。
言葉についても、個人差がさらに広がりやすい時期です。 2歳を過ぎると急にたくさん話し始める子もいれば、言葉は話さなくてもこちらの言葉をしっかり理解している子もいます。
1歳の時よりも違いが目立ってくるため、言葉が遅いと感じて不安になる親が増加する時期です。
また、2語文を話し始めたり、「なんで?」「どうして?」と質問をすることが増え、好奇心や興味がどんどん広がる時期でもあります。言葉数は少なくても、いろいろなものに対して興味を示し質問することが増えてきたら、言葉の覚え始めのサインです。まだ質問が少ない場合も、ゆっくり見守ってあげましょう。
言葉が遅い2歳児の特徴
言葉が遅い2歳の子どもには、次のような特徴があります。
- オウム返しが多い
- 単語のみで会話
- 要求が伝えられない
- 特定の遊びに固執
- 言葉で伝えずクレーン現象が多い
- 呼びかけての反応しない・反応が薄い
2歳になると、「ママ、行こう」「これ欲しい」など、2語文を話せるようになる子が増えてきます。また、質問や話しかけに対して同じ言葉を繰り返す「オウム返し」が見られることもあります。
オウム返しと聞くと、自閉症スペクトラム(ASD)の特徴と思われる方もいるかもしれません。 ですが、必ずしも自閉症とは限りません。
オウム返しには、いくつかの特徴やパターンがあり、その中には言葉を覚える過程で見られるものも含まれます。
| オウム返しの種類 | 特徴 |
|---|---|
| 成長過程で見られるオウム返し | 「りんご食べる?」と聞かれて「りんご食べる?」と言いながら手を伸ばす。質問の意味を理解している。 |
| 自閉症スペクトラム(ASD)のオウム返し | 言葉の意味を理解せずに反射的に繰り返す。コミュニケーションの意図がない場合が多い。 |
言葉が遅い2歳児へのサポート方法
言葉が遅いほかに気になる特徴が見られる場合は、市が行う発達相談や専門医への相談を検討しても良い時期です。 ただ、2歳頃は診断が難しく、「グレーゾーン」と診断されることもあります。

グレーゾーンとは、ASDや発達障害の特徴はあるものの、はっきりと診断できない状態のことです。診断がつかないと、「どうすればいいのか」と悩んでしまう親も少なくありません。

逆に障害名が急につくと、ショックを受けてしまう方もいますよね。
心の準備が必要な方は、病院ではなく発達支援センターや児童相談所で相談すると良いでしょう。医師ではないので診断がつくことはありません。気軽に子育ての相談ができます。
療育のスタート
言葉に遅れがあり、どうしたらよいか迷った時は、療育を検討してみると良いかもしれません。療育とは、発達の状態に合わせた発達支援行うサービスです。
たとえば、コミュニケーションの練習や、身の回りのことができるようになるトレーニングなどがあります。幼稚園や保育園違い、個別または少人数で行われるため、より細かいトレーニングが可能です。
言葉が遅れている場合は、言語聴覚士のいる療育を探してみるのも良いでしょう。
療育は、発達障害や自閉症などの診断がなくても、医師が「発達支援が必要」と判断すれば利用できます。グレーゾーンの子どもが、個別にサポートを受けられる場所でもあるため、「うちの子も行けるかな?」と思ったらまずは相談してみるのがおすすめです。
相談で親の悩みも解消
療育を始めてみると、「相談してよかった」と感じる親も多いようです。実際にサポートを受けることで、「一人で悩まずに済んだ」とホッとすることも少なくありません。
専門家に話を聞いてもらい、具体的なアドバイスがもらえると、子育ての不安や疑問も整理しやすくなります。診断がつかない段階でも、「とりあえず相談してみよう」くらいの気持ちで動き出すと、次の一歩が踏み出しやすくなります。
3歳以上 言葉が遅い子どもの特徴と対策

3歳を過ぎると、集団生活を始める子どもも増え、友達と一緒に遊ぶ機会が多くなります。走ったり、ジャンプしたりといった運動能力の向上。自分で靴を履いたり、着替えたりする自立心も強まる時期です。
言葉の面では、ほとんどの子どもはスムーズにやりとりができ、「貸して」「いいよ」など、簡単なコミュニケーションも可能です。社会のルールにも興味を示しはじめ、ごっこ遊びをする場面も多くなります。
好き嫌いがはっきりし、自己主張することも多くなるでしょう。自分から他人に目を向け始め時期でもあり、思い通りにならないことでケンカや泣いてしまう日も多くなります。
言葉が遅い3歳児以上の特徴
言葉が遅い3歳以上の子どもには、次のような特徴があります。
- 2語文が出ない
- 質問に対する反応が単調
- 一方的に話す
- 独語がある
- 友達と遊ばない、遊べない
3歳以上で言葉が遅い場合、「○○がほしい」や「○○に行きたい」といった2語文がうまく話せず、片言で話すことがあります。単語は出るものの、「りんご」「行く」といった感じで、文としてつながらないのが特徴です。
また、意思を言葉で伝えられないため、2歳児でも見られるクレーン現象が引き続き見られることもあります。質問に対しては「はい」「いいえ」で答えることが多く、話が続かないことも少なくありません。相手の反応を気にせず、一方的に話すことが目立つ場合もあります。
友達とうまく遊べないことや、集団の中で一人で遊ぶことが多いのも特徴です。
言葉が遅い3歳児以上へのサポート方法
3歳になると、発達障害の検査がより正確に行えるようになるため、医師が検査をすすめることが増えてきます。言葉の遅れが気になる場合は、3歳頃を目安に検討してみると良いかもしれません。
療育は併用がおすすめ
療育は、保育園や幼稚園に通いながら併用するのもおすすめです。幼稚園や保育園へ迎えに来てくれる療育を選べば、親の負担が少なくなります。
3歳頃の子ども達は、言葉が話せなくても仲よく遊べる年齢です。子ども自身が集団生活にストレスを感じていないなら、どんどん集団の場に慣れてもらいましょう。
小学校入学の準備も大切
年齢が上がるにつれ、親元から離れる時間も増えていきます。友達作りの目的もありますが、一番大切なのは、困っていることを伝える力を身に着けることです。
小学校入学後もスムーズに生活できるよう、今のうちから個別トレーニングを重ね、準備していきましょう。
なお、療育へ通ったからといって、小学校の普通級に通えなくなるわけではありません。むしろ、療育を通じて生活習慣や集団生活のルールを学ぶことで、普通級で過ごすための基礎習慣が身に付きます。
まとめ
言葉が遅いと、不安になることもありますよね。特に、発達障害やグレーゾーンと診断されることに抵抗を感じる方も多いでしょう。突然の診断にショックを受けてしまうこともあるかもしれません。
ですが、早い段階からトレーニングを始めることで、言葉の発達に良い効果が期待できます。無理に急がず、子どものペースに合わせたサポートを心がけることが大切です。
また、一人で悩まずに相談できる場所を見つけておくと安心です。発達支援センターや児童相談所、医療機関など、専門家の力を借りることで、今後の方向性が見えてきます。家庭でできる工夫や遊びを取り入れながら、少しずつ成長をサポートしていきましょう。
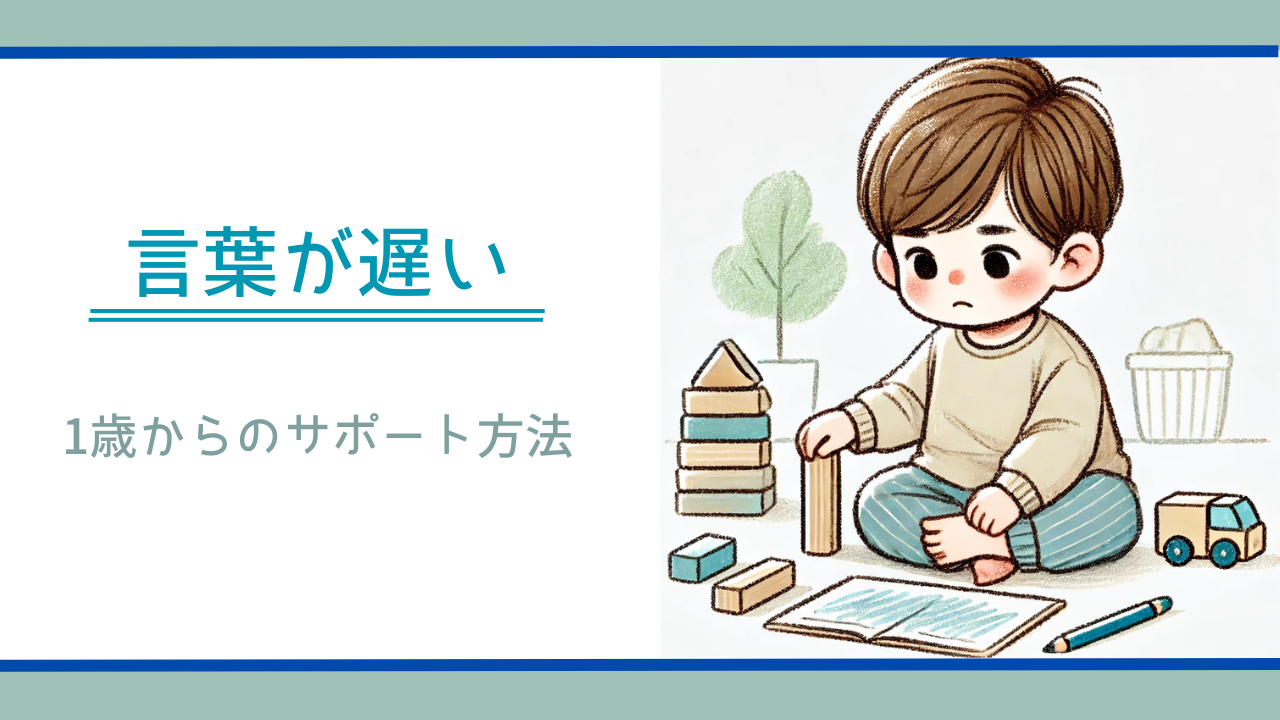

コメント